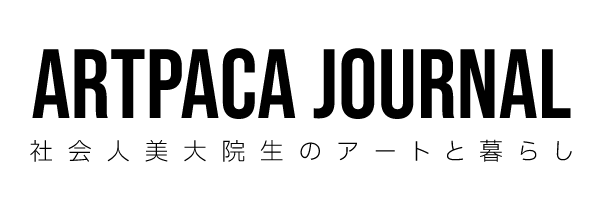前記事で《皇帝ユスティニアヌス帝と侍従たち》を取り上げるにあたり、数年ぶりにビザンティン美術について調べたのですが、改めてモザイク美術の美しさに魅了されてしまいました……。
そこでこの記事では、ビザンティン・モザイクについて調べたことを備忘的にまとめてみたいと思います。

ビザンティン・モザイクの技法
《皇帝ユスティニアヌス一世と侍臣たち》に代表されるように、ビザンティン美術のモザイク装飾の多くは、聖堂などの建築物の一部として作られています。
「構造物として下地が重要」であり、特に壁モザイクにおいては強固な下地が必要なため、下地は段階的に構築され、最終層には細かい砂を混ぜた石灰層が敷かれているそうです。この頑丈な下地が、1,400年以上もの間、作品の輝きを保ち続けるための基盤となっています。
モザイクとは、細かく砕いたガラスや石に色を施し、それらを隙間なく貼り付けて絵や図形、模様を描き出す美術技法です 。この小片は「テッセラ」と呼ばれ、漆喰やモルタルを地となる面に塗布し、その上にテッセラを貼り付けて模様を形成するのが特徴です 。
主要なテッセラ素材

ビザンティン・モザイクでは、多様な素材がテッセラとして用いられ、それぞれが作品の視覚効果と象徴的意味を表しているそうです。
ここでは、それぞれの素材を整理してみたいと思います。
石材
ビザンティンモザイクにて最も多く使われる素材は「大理石」です。
大理石は石灰石の変成岩で、色数が豊富。石の中では比較的柔らかいため、割りやすく加工しやすいという特徴があります。地中海沿岸で多く産出されたため、古代ローマ時代から主要なモザイク素材として利用されていました 。
その他の石材では花崗岩、アラバスタ(雪花石膏)、砂岩、蛇紋石、ドロマイトなども使用されています 。
ビザンティン・モザイクにおける主な用途
人物の肌や衣服、建築要素など、幅広い表現に用いられています。
色ガラス(ズマルト/smalto)
ズマルトはコバルトガラス(エナメルガラス)を粉砕して作られ、不透明でありながらも鮮やかなコバルトブルーが特徴です 。壁のモザイクは人が踏むことがないため、床モザイクでは破損しやすいガラス素材でも、壁面では彩度の高いズマルトを効果的に使用することができたようです。
ビザンティン・モザイクにおける主な用途
鮮やかな色彩表現に用いられ、とくに衣服や背景の細部、光の表現に効果的に用いられました。
金箔ガラス
ビザンティン・モザイクの最も特徴的な素材の一つが金箔ガラスです。
これは「平らな2枚のガラスの間に金箔や銀箔を挟んだ」テッセラで、金箔を埋め込むために窯で2回焼き上げて作られているそうです。表面のガラスに入る光の反射により、通常の金箔よりもはるかに鮮明な金色を放ち、高い耐久性も持ち合わせています 。
ビザンツ帝国時代にとくに発展し、聖堂を厳かに豪華に飾るために多用されました。特に「神やイエス・キリストのために使われる」とされ、黄金の輝きは神聖な光や天上の栄光を象徴する役割を担っていました 。
ビザンティン・モザイクにおける主な用途
皇帝や聖職者の光背、背景、神聖な雰囲気を醸成するために多用されました。
その他
このほか、古代のモザイクでは、真珠母貝、ラピスラズリ、テラコッタなども使用された例があるようです。
接着剤としてのモルタル
現代のモザイク制作ではセメントモルタルや接着剤が使われますが、ギリシャ・ローマ時代には「自然素材」である石灰モルタルが使用されていました 。
これには、ポッツォラーナ(凝灰岩の粉末)、川砂、大理石粉末、レンガ片が骨材として含まれていました 。ポッツォラーナは水硬性でセメントモルタルのような強い硬化力を持つ特性があり、これがモザイクの驚異的な耐久性を支えています 。
6世紀のビザンティン時代も同様の石灰モルタルが用いられたと考えられています。
制作工程と表現方法

作品からも伺える通り、当時のモザイクの制作工程は、高度な職人技と精密な計画が求められたようです。
石材やガラスは、モザイク専用のハンマーや割り台を用いて必要な形に細かく割られます 。現代ではダイヤモンド粒子が付着した刃が使われますが、ローマ時代には砂を付着させた青銅や鉄の鋸、砥石、サメの皮などが使われ、地道な手作業で行われていました 。
テッセラとテッセラの間には「目地」と呼ばれる隙間ができ、この目地がモザイク表現の重要な要素となります 。
目地の線の流れ、幅、深さ、色(使用するモルタルの色)によって、作品全体の表情が大きく変化します 。テッセラの並べ方にも、煉瓦積みに似た「馬目地」、タイルと同様に縦横の目地を揃える「芋目地」、四角いテッセラを基準にしながら目地をあえて揃えない「方形乱貼り」、不定形の破片をランダムに貼る「乱貼り」など、多様な技法が存在しました 。

特に壁のモザイクでは、わざと表面をデコボコに仕上げることで、光が乱反射し、モザイクがキラキラと輝いて見える効果を狙うことがありました 。
とりわけ金箔ガラスの輝きを最大限に引き出すために重要であり、聖堂内部を非現実的で超越的な空間へと変貌させ、観者に神聖な体験をもたらすことを意図していたと考えられています。
これらの素材や技法は、単なる美学的追求ではなく、神聖な光や天上の栄光を視覚的に体現し、信仰心を高めるための装置として機能していたことがわかります。
モザイク制作の複雑さもまた、ビザンティン・モザイクの特徴として挙げることができます。
数段階にわたる頑丈な構造の下地、専用の工具と熟練した技術を要するテッセラの加工、テッセラの配置における「目地」の重要性や多様な貼り方の存在などから、ビザンティン・モザイクの制作は単なる芸術的行為ではなく、高度な建築技術、素材科学の知識、そして卓越した職人技の融合であったと言えます。
このような複雑な工程を経て作り上げられたモザイク画は、膨大な資源が投入されており、いかに当時の社会において重要であったかを示唆していると言えるのではないでしょうか。
時代を超えて人々を魅了するビザンティン・モザイク

1400年以上も前の人々が、途方もない時間をかけて作り出したビザンティン・モザイク。
今回改めて調べてみたことで、その魅力の一端を改めて知ることができたように思います。
現代のような機械技術がなかった時代、こうした作品がどれほどの手間と時間をかけて作られたのかを想像するだけで、作品の重みが増して感じられるのではないでしょうか。
そしてその荘厳さこそが、ビザンティン・モザイクの魅力と言えるのかも知れません。